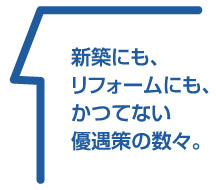
このところ住宅業界は、大都市も地方もすっかり冷え切ったままだが、住宅が内需拡大の大きな柱として、またぞろ脚光を浴びそうな勢いだ。
大都市では中堅どころのビルダーが相次いで倒産、年末、年度末に向かって先行きが大いに心配されるところだった。サブプライム問題から銀行も貸し渋りに走っており資金繰りの厳しい住宅・建設業界とっては危機的状況だ。しかし世界同時不況の様相となったことで、国も選挙どころではなくなり、緊急に大規模な経済対策を行わなければならなくなった。
このほど発表された総合経済対策では、内需刺激策として給付金とか高速道路料金の引き下げが大きな目玉となっているが、やはり最大の柱は今度も家電でも自動車でもなく住宅だろう。というのも、住宅産業というか建築生産の経済波及効果は2〜3倍あると言われている。建築は現場生産のため現場に各種資材や労働力が集まる。それだけでも地域経済に貢献するわけだ。住宅業界も過去にこうした内需拡大策の恩恵を何度もうけてきた。
そんなこともあり国交省でも積極的な施策を打ち出している。その柱となるのが住宅ローン減税の延長強化である。国交省が来年度以降計画している減税策などは
表の通りであるが、なんと言っても注目されるのは、200年住宅=長期優良住宅で控除対象の借入限度額が3600万円、控除額が650万円まで大幅に増額されることだ。これまで年間で最大十数万円が所得税から控除されるものが、一挙に50万円前後と3倍ほどになる。しかもこれまで所得税額からの控除だけだったものが、個人住民税からも控除するとしている。これは金持ち優遇といわれる制度の欠点をカバーしようというねらいで、「住宅ローン減税制度の最大控除額まで所得税額が控除されない者」については個人住民税から
|
 |
住宅の工事現場では、これまで以上に
工事管理が重要になる。 |
減額するとしている。
優遇策はこれだけではない。新築だけでなく住宅リフォームや省エネ住宅、断熱改修に対しても手厚い補助、税制優遇が用意されている。地球温暖化対策、CO2削減、低炭素社会の実現に向けて国も住宅の断熱・省エネ化は国際公約であり必死だ。
さらに驚くのはリフォーム工事にも税制優遇を適応しようとしていることだ。これまでリフォームでは、ローンを使ったものだけが税額控除対象となっていた。これをローンを使わないリフォームでも対象にしようというものだ。加えて、中古住宅流通の活性化とそれに伴うリフォーム工事でも、耐震改修を行った中古住宅をローンで取得した場合もローン減税する。新築一辺倒だった適用範囲をリフォーム工事、中古住宅まで大幅に広げた。それ故、今後リフォーム業界は新築以上に活発化する状況が見えている。
また今後の大きな住宅施策として掲げている200年住宅(長期優良住宅)の普及については、来年以降の税制優遇だけでなく、すでに「超長期住宅先導的モデル事業」として1棟200万円の補助金がスタートしており、大手ハウスメーカーや全建連などの工務店全国組織が取り組んでいる。来年度の予算要求では、この補助事業関連事業予算が130億円から200億円と大幅に増額されている。つまり今年1棟200万円の補助金がざっと5000棟分出ると言われているが、来年度ざっと1万棟に補助金が出る計算になる。補助を受けるは多くが戸建住宅と考えると、この1万という数字は考えてみると、新築30〜40戸の1戸の割で補助金が受けられるという凄い割合である。

