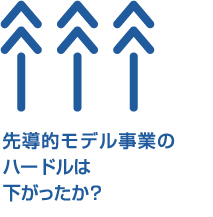
景気と先行きの話は別にして、いま住宅業界の最大関心事は何かというと、この欄でも何度も取り上げている長期優良住宅しかない感じだ。5月15日には今年度第1回の長期優良住宅先導的モデル事業の採択結果発表があった。昨年、200年住宅建設に200万円補助金が出るとして大いに業界の話題となったものだ。今年度もきっちり継続していて、大型経済対策の一翼を担って今年は170億円の予算が付いている。
さぞ、応募が多数あっただろうと思っていたら、昨年の第1回の半分ほど311件の提案しか集まらなかった。その理由をあれこれ考えてみると、昨年の採択された案件の内容などから見てずいぶんハードルが高い印象があったし、一方採択されたところでも受注にずいぶん苦戦したようなので、200万円の補助金は欲しいけれど面倒だしあまり効果がないという印象を与えたのかもしれない。
しかし採択された件数は昨年の第1回を大幅に上回る77件となり、数字的には採択率が2倍以上になった。長期優良住宅普及への国の意気込みを示す形になった。難しいし、あまり効果がないと考えて今回は応募しなかった業界関係者にとっては、「しまった!出しておけばよかった」という気持だろう。
で、今回採択されたモデル事業の中身を見ると、「住宅の新築」が58件、「既存住宅等の改修」が9件、「維持管理・流通等のシステムの整備」が6件、「情報提供及び普及」が2件。住宅の新築では木造等循環型社会形成分野の提案が24件と最も多く、つづいて維持管理流通強化分野で13件、共同住宅はわずか4件であった。
あまり聞きなれない「木造等循環型社会形成分野」というのは何かというと、平たく言えば国産材・地元材を使って長期優良住宅を建てましょうというもの。この分野で応募した案件が一番多く採択された。また「維持管理流通強化分野」は、家を長持ちさせるメンテナンスサポートや住宅履歴の活用に重点を置いた家づくりのことで、簡単に言えば「中古住宅として売る時も性能がちゃんと証明できる」家づくりのことだ。この2つの分野で37件が採択されており、全案件の半数に達している。(詳しくは、建築研究所のホームページ、
http://www.kenken.go.jp/chouki/を参照)
つぎに採択された企業を見てみると、木造等循環型社会形成分野の提案では「宮城の伊達な杉」、「ぐんま森林物語」、「岐阜美濃の家」「丹沢桧で造る相模の家」などと地域名を冠し地元材をつかった提案が多く採択された。こちらは企業規模をみると地域の工務店・ビルダー、地域グループなどが多かった。それに反して維持管理流通分野では、積水、大和、ミサワ、トヨタなど大手ハウスメーカーがずらりと名前を連ねた。
国産材の活用で地域のビルダーやグループが多いのは分かるが、維持管理流通で大手ハウスメーカーの名前がどうして並ぶのか。いろいろ考えてみると、大手ハウスメーカーであれば「性能や造りがしっかりしているし、維持管理も長年にわたってちゃんと見てくれるので、将来的に中古住宅として流通させても安心ですよ」ということだろう。それは国の意向なのか、評価委員のたまたまな評価なのか、さらには消費者の意識なのか分らないが、この分野で採択された企業名はその意図するところを明確に示している気がする。中小工務店に頑張ってもらいたい筆者としては、なんだか元気が出ない結果に見えてくる。
また、今回採択された企業・グループは昨年に比べ多くなったが、実際は昨年度の超長期優良住宅先導的モデル事業に採択されていたところも20数社あり、まったくの新規提案は50数社で、それほど採択のハードルが下がったわけでもなかった。国の意向としても、連続採択によって引き続き発展的に長期優良住宅の普及啓蒙に努めてくださいということもあるので、新規の応募はやはりハードルが高いと言わざるを得ないようだ。

