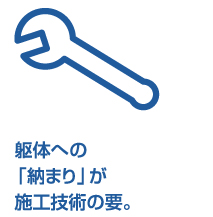
また一方では、業界内でも積極的にプロユーザー(大工・工務店など)向けのネット販売に取り組むところが多くなってきた。インターネットが華々しく普及し始めた10年ほど前、建材のネット販売も登場したが、その後既存ルートからの圧力や価格の不透明さなどで、成功したとはいえなかった。加えて工務店の信用問題、取引方法や物流などで様々な問題点もあった。そうした事情を乗り越えて、最近またネット販売が増加してきた理由は、価格の安さや商品バリエーションだけでなく、バラ売り・1個でも注文できるし宅配便による現場納品もOKなど、その便利さにある。また決済も前金、代引きなどが一般的なネット販売の普及で当たり前になり、業界でも常識になってきたからだ。
小誌(新・住宅ジャーナル)にコラムを書いているバットマン・高橋氏もネット販売を行っている一人だ。聞くとリアル(地域市場)での建材販売は非常に厳しいとのことだが、ネット販売は伸びているそうだ。取引口数は4500社に増え、月間数百万円の売上があるという。高橋氏によると「まだ建築金物が販売の中心」と控え目な解説だが、ネット販売の将来性には自信がある様子がうかがえる。
そうすると、将来日本の住宅産業では一般ユーザーもプロユーザーもネットで建築資材を自由に調達することが当たり前になるかもしれない。日本だけでなく世界中の建材・設備が現場にやってくる。あとは職人や専門技術者を集めて施工するだけで住宅が出来上がる。
ただ、そこに落とし穴がある。なぜかというと設備や建材は住宅に取り付いて初めて商品価値を持つからだ。躯体にどう取り付けるか=「納まり」をどうつけるかが現場施工技術の要である。これは躯体と材料の特性をよく知らなければうまくいかないことは、現場のベテランならばよく知っていることである。だから「好き勝手なものを現場に持ってきて取り付けてくれと言われたってクレームのもとだ」ということになる。
逆に言えば、それをクリアーできれば誰だってどんなものでも持って来られることになる。ビルトインタイプのドラム式洗濯機を輸入販売しているメイコー・エンタプライズの佐々木社長は、国内メーカーがビルトインからほとんど撤退したのは、水漏れ対策が十分でなかったからだと指摘する。水漏れの原因となるドラムの震動をどう抑えるかという機器性能に加えて、施工上のポイントがある。同社が長年ビルトインを手掛けているのはそのポイントを熟知している賜物であるというのだ。最近はネットを調べて問い合わせてくる客も多い。性能と施工基準が明確であれば、世界のどこからでも製品を持ってきて取り付けることができるというわけだ。
