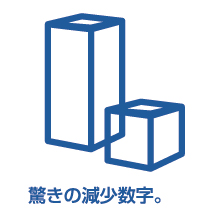
いくつか驚きの業者減少の数字を拾ってみる。まず公共工事がジリ貧状態のゼネコン。その関係の総合工事業では01年に比べ7.9%減少し約23万事業所。最悪は一般土木建築工事業(いわゆる土建屋さん)で24.4%減少。工務店と同じく1/4が消えた。そのほか鉄骨・鉄筋工事、石工・れんが等工事、左官工事業者が同じく25%前後減少した。しかし工事業者が軒並み減少したのかと言えばそうでもない。
06年の調査では総合工事業からその他の設備工事業まで25業種に分類されているうち、プラスだったのは、建築リフォーム工事業、床工事業などわずか5業種だった。今回の調査では、建築工事業をはじめ専門工事など16業種がプラスになった。2000年以降減少を続けていた建設業分野の各業種だったが、05年の姉歯事件、06年の住宅生活基本法を境目にして、業界の様相が大きく変わった。そのことが工事業界にも相当影響していることが、この数字から見えてくるのだ。元請関係が大きく沈み込み、リフォームを筆頭に、比較的新しい床工事、内装工事、設備、電気通信関係が勢いを増したり、盛り返したりしているのである。建築リフォーム工事業は、まさに時代の風や国の施策の支援を受けて、01年の5000から1万4000とざっと3倍の事業所数になっているのである。
しかし、全く振るわなくなった業種、業界もある。昨年公共建築物等木材利用促進法がスタートしたが、製材、木材加工関連の事業所数の動向を見ると暗い気持ちになってくる。業界では法律の施行で国産材がブームになると意欲満々だが、このセンサスの数字を見る限り、供給は本当に大丈夫なのと心配になってしまうのだ。30年以上前には3万業者いた製材関連であるが、調査の製材業・木製品製造業では今回7821事業所で、01年に比べ32.8%減と、10年足らずの間に1/3が消えた。製材からプレカット加工、合板、造作材、建具などを製造する事業所が木材・木製品製造業という調査の分類であるが、この項目に入る製造業は、その他の家具・装備品製造を除いて殆ど3割前後の減少である。木材加工では、木質系の加工品であれば内装ドアや建材等が殆ど日本から中国、東南アジアに工場がシフトしていたはずであり、こうした現象を示すのも当然だったろう。

