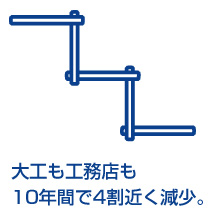
ところが一方で、大いに気になる数字もある。6月末に2010年国勢調査の抽出速報集計が発表されたが、それによると大工人口は39万人で、5年前の国勢調査から14万人減少した。2000年は64万人であったので、わずか10年間で25万人もの大工がいなくなった。4割近い減少である。また経済センサスを見ると木造住宅建築工事業、いわゆる工務店の事業所数もこの8年間で26.6%減少し6万7000となった。住宅着工が14ヵ月も伸びていると言っても、なかなかピンとこないのは、こうして同業者や大工が回りからどんどん消えていくので、実感として業界の不況感がぬぐえないからだろう。この流れは大工や工務店だけではなく、建設関連のほとんどの専門工事業・各職方で起きている。
新築需要は、これから5年間くらいは、低金利や消費税アップの動向、優遇税制などで、よほどの世界的な経済ショックでもない限り堅調に推移すると思うが、問題は現場の生産キャパシティーの減少である。現場生産の担い手である大工などの職人が極端に少なくなる時代を迎えた。十分な需要があっても生産が出来なくなるのではないかと心配するのである。
本当にそんなに生産能力が落ちるのだろうか。05年の大工数は約53万人であった。この人達が全員在来木造住宅を作っていると仮定しよう。今時の木造住宅では1坪生産するのに1人前の大工が1.5〜2人掛かっている。そうすると大工の1日辺りの生産坪数は0.5坪〜0.7坪と言うことになる。筆者の調査では大工は年間230日程度働くから、大工1人当たりの年間生産量は、1日0.6坪として138坪(230×0.6)である。1人当たり3〜4戸建てている計算になる。総生産坪数は約7300万坪(138×53万人)が在来木造1年間の最大生産量である。
しかし国勢調査では15歳から60歳代以上の大工もカウントしているし、全員が在来木造住宅の生産に携わっているわけでもない。マンションの造作、リフォーム、非住宅など大工の活躍する場は多いので、その半分と仮定してみると、在来木造住宅の年間生産量は3650万坪となる。最近の平均的な木造住宅1戸の床面積を36坪としてみると、ざっと101万戸である。05年の実際の木造住宅の着工数は54万戸であった。この当時どれくらい大工が余っていたのだろうか。数字的には半分が仕事をしていなくても生産できた形だが、現実にはそれほど職人が余っていたとも思われない。
では、上記の考え方で昨年の大工の生産能力を見てみると年間2690万坪が最大の生産量である。戸数では約75万戸だ。実際には46万戸木造住宅が建築された。最大生産量との差は29万戸、5年前と比べてその余裕が大幅に縮小している。つまり大工は忙しくなってきたし、不足度が増してきているのである。実際にそうした傾向が各地で見られるようになっている。またリフォームなどでは大規模改修やリノベーションが増大しており、かつての設備取り替えリフォーム時代に比べて大工需要は増大している。
問題は、これから5年後である。同じ方式で計算してみよう。まず大工人口がこれまでの減少率で減っていくと想定すると、5年後30万人を確実に切ることは間違いない。30万人としてみると、木造住宅の最大生産量は年間2070万坪。戸数にすると58万戸だ。最大でこれしかないのだ。先によほどのことがない限り今後5年間住宅着工は堅調に推移するといったが、このように現場の生産がほとんど間に合わなくなるのである。なぜなら年間80〜90万戸の住宅着工があれば、その半分が木造住宅であるから大工の生産能力ぎりぎりの数字である。加えて、消費税アップ前の駆け込み需要で100万戸を突破するようなことにでもなれば、現場生産はパンクする。これは大工職だけの話ではない。下職、専門工事職全体の話である。国はリフォーム市場を倍増すると言っているが、そのニーズに応えるだけの現場職人の確保は、現状のままではほとんど絵空事であることが分かる。
そして、現場では何が起きるかと言えば職人の争奪戦だ。資金力のあるところ、年間を通じてコンスタントに仕事を持っているところしか、職人は集まらなくなる。大手優位は益々進み、地場の中小工務店は、この職人確保の壁に打ちのめされるかもしれない。
こうした決定的な大工不足、職人不足に打ち勝って行くには、公的機関による大量育成をすぐに始めることも必要だが、工務店等での自社での育成も必要だ。さらには現場生産のこれまでに倍する合理化、生産性向上が必要だろう。現場生産をスピードアップするためのシステム、施工方法、部材開発も絶対進めなければならない。
