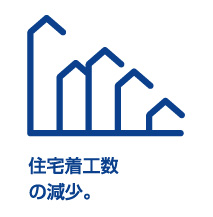
絶好調のアベノミックスも、ここのところの円安、株価乱高下で「本当に今後も大丈夫なの」、「中小企業、庶民レベルまで景気が良くなる前に息切れするんじゃないか」などなど、不安や疑問が出てきた。
そんな疑問を払拭しようというわけではないだろうが、このほど規制改革に重点を置いた成長戦略第3弾が発表された。それによると、「国家戦略特区」の創設や薬のインターネット販売の解禁などの目玉施策を上げたほか、10年後には、1人当たり国民総所得(GNI)を150万円以上増やす目標を掲げた。
では住宅産業の状況はどうだろうか。安倍政権では経済の再生に向けて、?大胆な金融政策?機動的な財政政策?民間投資を喚起する成長戦略という「三本の矢」を放っているが、その矢はどこまで来ているか。そして住宅産業、我々木造住宅業界の成長戦略は何だろうか。しかし改めてそれを考えると、不安なことばかりが頭をよぎる。
今住宅業界は非常に忙しい。ご存じの通り消費税増税を前にした駆け込み需要だ。しかし、ここに来て足踏み状態が見えるようになってきた。その最大の原因は大工不足、専門職不足だ。そのことは前回のコラムでも指摘した。さらなる不安は少子高齢化だけでなく、総世帯数の減少による市場縮小だ。これも急速に迫ってきている。
今年初めに公表された「日本の世帯数の将来推計」では、6年後の2019年5300万世帯をピークに減少に転じるとしている。そして2035年には4950万世帯まで減るというのだ。国の機関の推計だから結構甘いと思うが、それでもたった15年間くらいで400万世帯が消えてしまう。
これを住宅着工数で考えてみるとどうなるか。日本住宅ストック数は2008年時点で5700万戸。現在は6000万戸前後ではないかと思われる。では今後20年間程度でどれだけ住宅ストックが増えていくのだろうか。
おおざっぱに見当を付けてみる。まず毎年の着工数だが、大手シンクタンクによると2020年までは毎年80万戸程度は家が建つということだから、その数字を採用する。その後は世帯数が減少すると推計されているので、2021年〜2035年の15年間は毎年50万戸としてみる(50万戸という数字は、今ある住宅産業としては生き残るための最低ラインと思う)。そうすると2035年時点の住宅ストック数はどうなるか。
2020年までの合計は約400万戸、その後の15年間の合計が750万戸。統計によると毎年の着工数に対して10数%の滅失住宅があるので、それを考慮すると増加する戸数はざっと980万戸、住宅ストックの合計は7000万戸になってしまう。
2035年の世帯数が4950万世帯ということだから、ざっと2000万戸が空き家となる。世界一の空き家大国だ。本当にこんな事態が起きてしまうのだろうか。
国の推計はいつも甘いと批判されているので、事態はもっと深刻なはずである。そう考えると今後の毎年の住宅着工はさらに低めの予測とならざるを得ないはずである。これでは、住宅産業の成長戦略なんか全く描けない、という結論になってしまうだろう。
昨年から国が中古住宅流通やリフォームを叫びだしたのは、こうした背景があるのだ。
