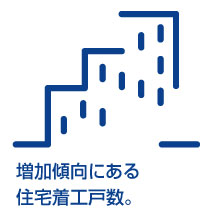
昨年1年間の新設住宅着工戸数が発表された。大震災で大幅な落ち込みが心配されたが、結果は83万4117戸で、前年比2,6%増と2年連続の増加となった。これは、たぶん業界の皆さんの実感としても違和感がない数字だと思う。この欄でも何度か述べたが一昨年の後半から大都市圏をはじめ全国的に市場が活発だったし、景況感は、3,11以降一時ストップしたものの、5月以降は順次回復した。また、秋以降も全国的に繁忙感があり、震災被害の甚大だった東北3県をみても、仙台周辺などの市場が大きい地域は住宅需要が旺盛で、職人不足と相まってバブル状態となっている。原発事故で住民避難が続く福島県でさえも、避難地域外などは人口流入もあって忙しい状況だ。
また職人不足も全国に広がっており、震災復興地域だけでなく、首都圏での逼迫感は相当なものになってきている。さらに、四国、九州などでも職人不足の声は大きくなってきている。そのせいもあり、業界の感触としては、冒頭の数字以上の繁忙感を感じているのではないだろうか。
今回発表された平成23年(暦年)着工統計をざっと見てみると、利用関係別の戸数を見ると持家が30万5626戸(0,1%増)、貸家が28万5832戸(4,1%減)、分譲住宅が23万4571戸(16,2%増)で、唯一貸家がマイナスとなった。分譲住宅の中身を見るとマンションが11万6755戸(28,9%増)と大幅な増加となり、一戸建も11万6798戸(5,8%)と伸びた。
また地域別の動向では、昨年に比べ北海道が11,5%増、沖縄が10,4%増、九州が8,6%増と10%前後も増加した他、中国、関東、四国、北陸が数%の増となった。マイナスは東北の4,3%減をトップに、中部、近畿の3地域のみだった。3大都市圏別でみると首都圏は5%増でプラスだが中部、近畿圏ともマイナス。3大都市圏以外のその他の地域が3,3%増だった。3大都市圏別の傾向を見ると分譲住宅の供給で首都圏とその他の地域が20%内外の高い伸びを示した。理由はマンションの供給が大幅に増えたことで、首都圏では34,1%と大幅に伸びたほか、その他の地域では54,5%増の1万8953戸と大量に供給された。
